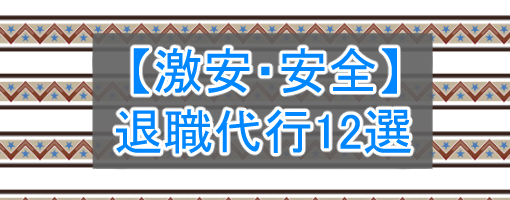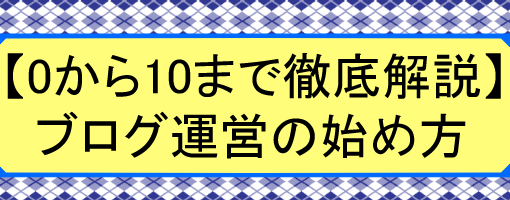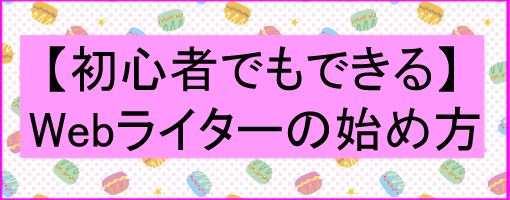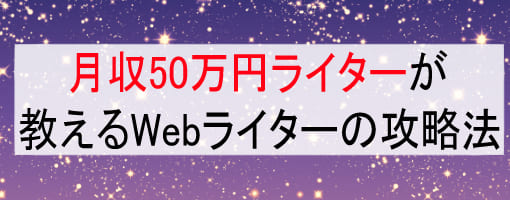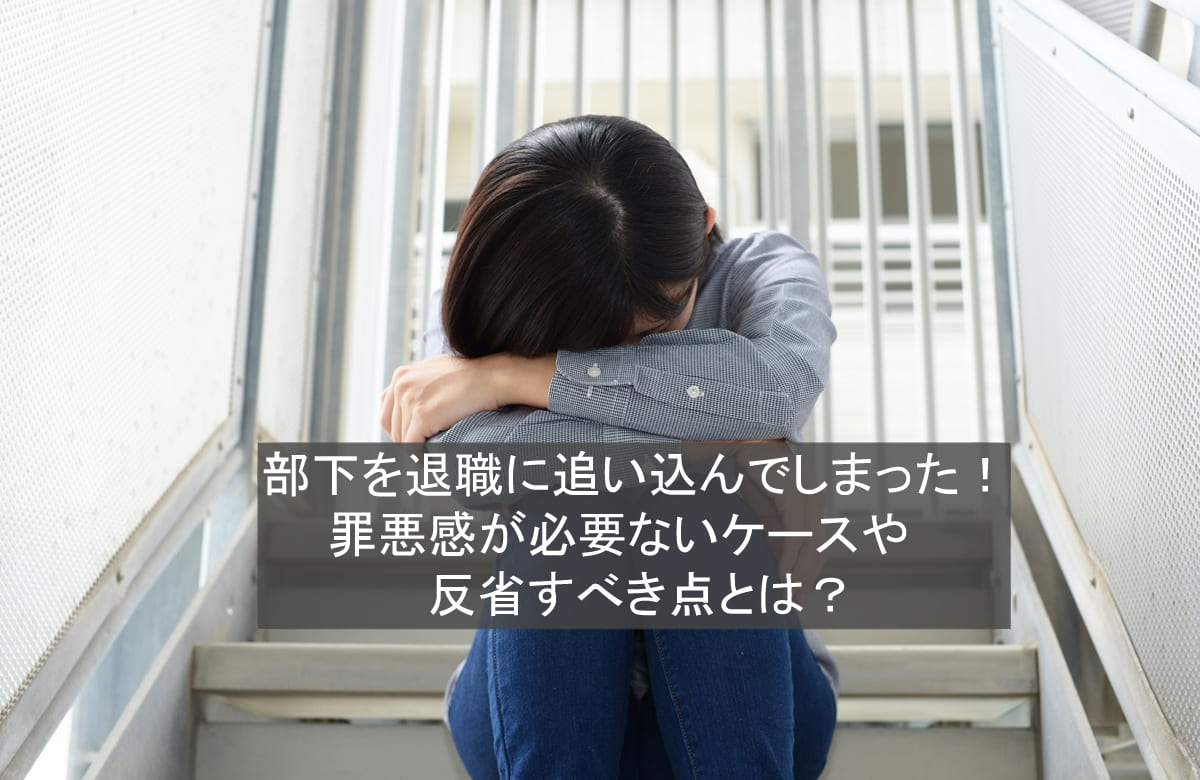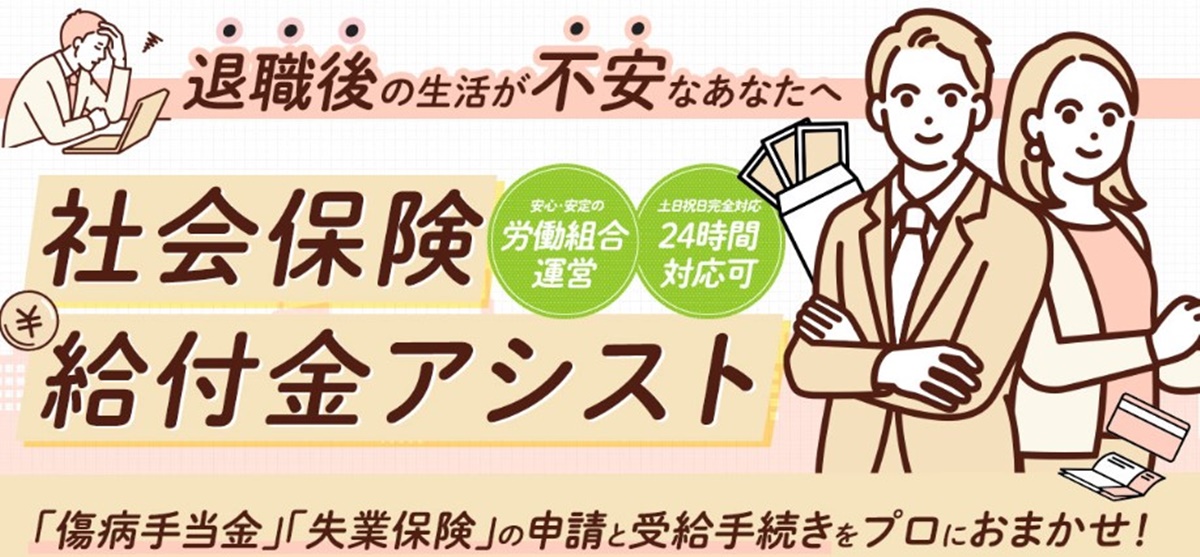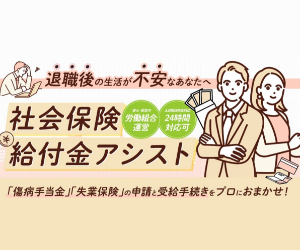・部下を退職に追い込んだ場合に罪悪感を感じる必要がないって本当?
・同じミスを繰り返さないようにするためにはどうすれば良い?
本記事ではこのような悩みを解決できます。
本記事の要点
本記事の執筆者
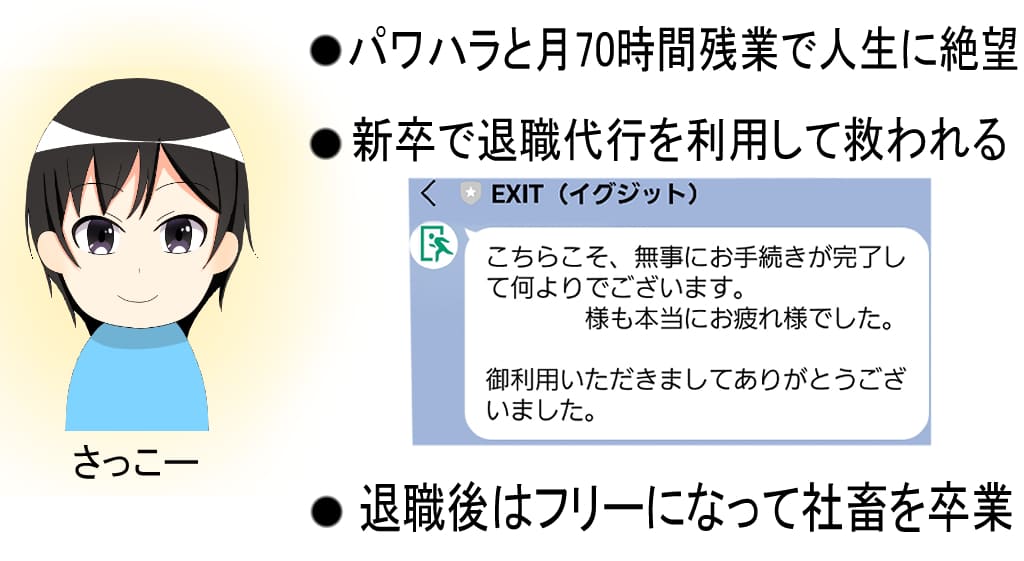
さっこー(@sakko1878)
あなたが部下を退職に追い込んでしまった場合、罪悪感を感じることもあるでしょう。
しかし、退職に追い込んだからといって必ずしも自分が悪いとは言えません。
この記事では、退職に追い込んでしまった場合に罪悪感を感じなくても良いケースや、反省すべきケースを紹介しています。

\退職後の生活費でお困りの方へ/
社会保険給付金アシストでは、社会保険給付金の申請サポートを実施しています。
条件によっても異なりますが、数十万円から数百万円の給付金を受け取れる可能性があります。
【おすすめポイント】
- 最大28か月間にわたって総額数十万円から数百万円の受給
- 利用者は無料で退職代行を利用可能
- 完全オンラインでサポート
- 受給できなければ全額返金
- 1,000人以上の利用者
- 顧客満足度98%
- 24時間365日対応
【利用条件】
- 年齢が20歳~54歳である
- 退職日が本日から14日~90日未満である
- 現時点で転職先が決まっていない
- 社会保険に1年以上加入している
-

-
社会保険給付金アシストは怪しい?口コミやメリット、デメリットを紹介!
部下を退職に追い込んでしまったときに罪悪感を覚える3つの理由

部下を退職に追い込んでしまったときに罪悪感を覚えるのは以下が原因です。
部下を退職に追い込んでしまったときに罪悪感を覚える理由
- ひとりの人生を変えたような気分になる
- 残った人の業務量が増えた光景を見て申し訳なくなる
- 採用活動に奔走する上司を見て後悔する
では3つの理由を詳しく紹介します。
理由1.ひとりの人生を変えたような気分になる
退職は人生において大きなイベントなので、自分が退職させたとなると罪悪感が生じます。
たとえば、退職した人がその後の人生に苦労したと聞けば心が痛むでしょう。
「あの時自分が退職に追い込んだから不幸な人生を歩んでしまった」と不安になりがちです。

理由2.残った人の業務量が増えた光景を見て申し訳なくなる
部下が退職してしまうと、残った人たちの負担が増えることがあります。
たとえば、退職した部下の仕事を引き継がなければならないため、残った人たちの業務量が増えたり、残業が増えたりします。
人がいなくなってから明らかに忙しくなると「自分のせいでみんなに迷惑が掛かっている」と思いがちです。
場合によっては、ほかの従業員から冷たい目で見られる可能性もあります。

理由3.採用活動に奔走する上司を見て後悔する
部下を退職に追い込んでしまった場合、新しく人を雇わなければいけません。
しかし、人を雇うのにも時間やコストがかかります。
新人を雇うのに苦労している光景を見ると「自分のせいで迷惑をかけた」と感じるでしょう。
また、人を新しく雇うと指導も必要です。
指導の際はほかの従業員が必要になり、結果的に1人あたりの業務量も一時的に増えます。
社内全体で忙しい様子になると、罪悪感もひとしおです。
退職に追い込んでしまっても罪悪感を覚える必要がない3つのケース

退職に追い込んでしまうと罪悪感を覚えがちですが、以下のケースは罪悪感を抱える必要はありません。
退職に追い込んでしまっても罪悪感を覚える必要がないケース
- 辞めた人に問題があった
- 正当に注意しただけで辞めた
- 自分以外の部分にも問題があった
辞めた人や会社に問題がある場合は、必ずしも自分が悪いとは限りません。
では罪悪感を覚えなくても良いケースを具体的に見ていきましょう。
ケース1.辞めた人に問題があった
以下のような問題がある人を退職に追い込んでしまっても、罪悪感を感じることはありません。
- パワハラやセクハラなどのハラスメントを行っていた
- 真面目に働いていなかった
- 社内のルールを守っていなかった
社会人として悪質な要素がある場合、辞めさせたところで自分が責められることもありません。
むしろ「会社のためによく言ってくれた」「代表して辞めさせてくれて助かった」と感謝されます。

ケース2.正当に注意しただけで辞めた
軽く注意しただけで辞めた人に対しても罪悪感を覚える必要はありません。
最近では少し怒っただけで辞める人もいます。
たとえば、「なぜマニュアルを参考にして仕事しないのか」と注意しただけで辞める人もいるでしょう。
正しいことを軽く注意しただけで退職に追い込んでしまった場合、余計に罪悪感を感じることもありません。
ただし、伝え方や態度によっては結果が変わります。
威圧的な怒り方ではなければ問題視されませんが、場合によっては上司から注意されるでしょう。
ケース3.自分以外の部分にも問題があった
部下が退職に追い込まれた場合、会社に原因がある可能性も存在します。
- 社内の雰囲気が悪い
- 業務の進め方に問題がある
- ルールが敷かれていない
- 単純に仕事が合わなかった
- 上司にまともな人がいなかった
会社に不満がある場合、すでに辞めたいと感じている可能性が高いです。
辞めたい気持ちが強い中、上司が注意することで退職を決断する人もいます。

退職に追い込んでしまったときに問題となる4つのケース

退職に追い込んでしまった際に問題となるケースは以下のとおりです。
退職に追い込んでしまったときに問題となるケース
- パワハラやいじめで退職に追い込んだ
- 強い言葉やきつい態度で接した
- 新しい人に自分と同等のレベルを求めてしまった
- 複数人にあなたのせいで辞めると言われた
明らかに自分のせいで部下が辞めてしまった場合は、しっかりと反省すべきです。
同じミスを繰り返すと悲惨な末路を歩むので、同じミスは繰り返さないようにしましょう。

1.パワハラやいじめで退職に追い込んだ
パワハラやいじめで退職に追い込んでしまった場合、大きく問題となります。
パワハラやいじめは被害者の退職だけでなく、周りの社員にも悪影響を与えがちです。
具体的には、以下のような問題が起こります。
- 周囲の社員のモチベーション低下
- 信頼関係の損失
- 法的問題の発生
会社全体に悪影響を及ぼすと、自分が退職に追い込まれるリスクもあります。

2.強い言葉やきつい態度で接した
強い言葉やきつい態度で接することは、部下をストレスやプレッシャーにさらし、退職に追い込んでしまいます。
きつく対応された部下は「自分には何の能力もない」と感じてしまい、自信の喪失につながりやすいです。
たとえば、プレゼンテーションの場で発言が強く非難されたり、自分の意見を否定され続けたりすると辞めたいと感じます。
怒られる経験を繰り返すと辞めるのも遅くありません。

3.新しい人に自分と同等のレベルを求めてしまった
優秀な人にとってありがちなのが、新人に高いレベルを求めることです。
新人に対して経験者レベルのスキルを求められても、まともに動けません。
たとえば、入ってきたばかりの人に対して「もっと効率よく動いて」というのは間違いです。
過度に期待されると新人はプレッシャーを感じて辞めてしまいます。
特に仕事ができる人は、部下に対しても高いレベルを求めがちです。
しかし、いきなり動ける新人は限られるので、相手のレベルに合わせて指導しなければいけません。

4.複数人にあなたのせいで辞めると言われた
辞める人の大多数から「あなたのせいで辞める」と言われた場合は、しっかりと反省すべきです。
複数人から辞める原因とされるときは、自分の何かが嫌だと思われています。
たとえば、パワハラをしている人だと一緒に働けないので、退職理由の際に言われやすいです。

退職に追い込んでしまったことを反省しない人の末路3つ

自分の言動が原因で退職に追い込んでしまったのに反省しないと、以下の末路を歩みます。
退職に追い込んでしまったことを反省しない人の末路
- 社内のトラブルメーカーとして扱われる
- 社内における評価が下がる
- 今度は自分が退職に追い込まれる
続いて3つの末路を詳しく見ていきましょう。
末路1.社内のトラブルメーカーとして扱われる
退職に追い込んでしまったことを反省しない人は、ほかの社員からも嫌われていきます。
たとえば、人を辞めさせるような人とは、なるべく関わりたくないと考えるのがふつうです。
信用が下がると徐々にコミュニケーションの機会も減り、まともに相手してもらえなくなるでしょう。

末路2.社内における評価が下がる
退職に追い込んでしまった人は、同じようなミスを繰り返すと評価してもらえません。
本来であれば、会社で貢献すると給与やボーナスが増えます。
目に見えるかたちで評価されると、よりモチベーションも上がるでしょう。
しかし、部下を退職に追い込むような問題行動が多い人は評価できません。
ずっと同じ待遇で働くことになるため、モチベーションも低下しやすいです。

末路3.今度は自分が退職に追い込まれる
退職に追い込まれることを反省せず、同じような行動を繰り返す人は、逆に自分自身が退職に追い込まれる可能性があります。
- 仲間からの信用を失う
- 人間関係が悪化する
- 仕事の品質が低下する
悪質な行為は基本的に自分に返ってくるため、反省しない人は辞めさせられる可能性が高いです。

退職に追い込んでしまったときに見直すべき4つのこと

退職に追い込んでしまった人は以下のポイントをチェックして、自分に非があったかどうか確認しておきましょう。
退職に追い込んでしまったときに見直すべきこと
- 接する態度が強くなかったか
- 理不尽に怒らなかったか
- 怒ったあとにフォローを入れたか
- 普段からコミュニケーションを積極的にとっているか
もし上記に当てはまる場合は、次に生かすために直すべきです。
では反省すべき4つのポイントを具体的に紹介します。
ポイント1.接する態度が強くなかったか
退職に追い込んでしまったとき、まず自分自身の接する態度について見直す必要があります。
自分が過剰に厳しく接していた場合、部下が退職に追い込まれる原因となりやすいです。
- 指示や要求を押し付けた
- 過剰に期待した
- 悪意のある行動や態度を取った
- コミュニケーションを避けていた
- 期待に応えられなかった場合に批判的な態度を取った
上記のような態度を取っていた場合は原因を探り、今後は相手と適切なコミュニケーションをとるように努めましょう。

ポイント2.理不尽に怒らなかったか
理不尽に怒ってしまうと、上司や同僚との関係が悪化し、退職を決断する人もいます。
意味なく叱ることは、職場での人間関係を悪化させ、ストレスを与えることになります。
- 相手を傷つける可能性がある
- 相手に対する信頼や尊敬を損ねる
- 関係性が悪化し、職場環境が悪くなる
部下を特別な意味なく怒ってしまった場合は、反省して改善することが大切です。
どうしても怒ってしまいがちな人は、以下のような対策をとりましょう。
- 冷静な判断をするために、怒りをコントロールする
- 相手の立場や気持ちになって考える
- 相手に対して尊重の意を示す
- 感情的になる前に、相手と話し合いをする時間を作る
- 感情コントロールの本を読む

ポイント3.怒ったあとにフォローを入れたか
事情があって部下を怒った場合、フォローを入れることが大切です。
フォローアップが入らなかった場合、相手に傷つけたり誤解を招く可能性があります。
たとえば、上司と部下の間である不一致が起きたとします。
上司が突然、部下に対して怒鳴りつけたり、罵倒するような言葉を使ったりした場合、部下はショックを受けるでしょう。
しかし、その後に上司が謝罪したり、話し合いを持ったりすることで、部下は不快な思いを解消できます。
逆に、上司が何も言わず、そのまま放置する場合、部下は上司に対する信頼を失い、退職を決意するかもしれません。

ポイント4.普段からコミュニケーションを積極的にとっているか
普段からコミュニケーションをとっておくと以下のメリットがあります。
- 部下を叱った場合でも関係が悪化しづらい
- トラブルが発生した際に解決しやすくなる
- 自分自身の意見や考えを相手に伝えることができ、仕事の成果にもつながる
- 職場でのストレスや不安感が軽減され、健康的な職場環境を作れる
上司や同僚との円滑なコミュニケーションが取れるかどうかは、業務を遂行する上での重要な要素です。
特に、トラブルが発生した際に、コミュニケーションがうまく取れているかどうかは問題解決の鍵を握ります。
上司から積極的に会話していれば、部下が退職に追い込まれることもないでしょう。

まとめ.退職に追い込んでしまった場合は同じミスを繰り返さないようにしよう!

本記事の要点
- 自分が直接的な原因でない退職なら罪悪感は不要
- 自分が責任で退職に追い込んでしまった場合は原因を振り替えるべき
- 反省しないといつか自分が退職に追い込まれる
部下を退職に追い込んでしまった場合は罪悪感を覚えがちですが、自分が原因でなければ悪いと思う必要はありません。
たとえば、辞めた人間や会社に問題があって、結果的に自分が退職に追い込んだ場合は罪悪感が不要です。
一方で部下を厳しく叱りつけたり、いじめたりした場合は自分の行為を反省しましょう。
次も同じことを繰り返すと社内で浮いた存在になり、最終的に自分が退職に追い込まれます。

現在や退職後のキャリアに悩む方へ
「退職後に何をすべきか迷っている」
「自分に合っている仕事がわからない」という人にはポジウィルがおすすめです。

ポジウィルでは自己分析や企業分析、自己認知を通してキャリアを作っていきます。
トレーニングを通して、自分が本当に望むキャリアを見いだせるのが魅力です。
- 自分が本当にやりたいことを探している
- 自己分析が上手にできない
- 今度こそは転職に失敗したくない
- 初めての就職でわからないことが多い
- 年収アップやキャリアアップを目指している
- キャリアのことを気軽に相談できるパートナーがほしい
- 仲間と一緒にがんばりたい
上記に当てはまる人は、無料カウンセリングを受けてみましょう。